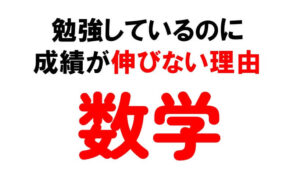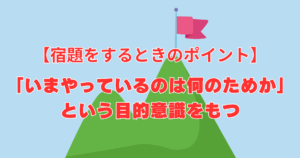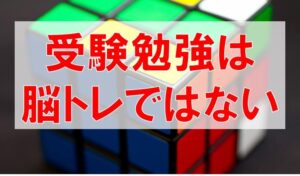鹿児島市の中学受験に向けた4年生算数の勉強法|まず身につけるべき3つの力とは?
中学受験を目指している鹿児島市の小学4年生とその保護者の皆さん、こんにちは。
「そろそろ受験勉強を本格的に始めなきゃ」と思いながらも、何から手をつけたらいいか迷っていませんか?
特に算数は、受験の合否を左右する最重要科目のひとつです。
だからこそ、4年生の段階で「基礎」をしっかり固めておくことが、これからの成績を大きく左右します。
本記事では、中学受験に向けた算数の基礎固めとして、4年生で絶対に身につけておきたい3つの力
- 四則演算
- 逆算
- 線分図の作図
について解説します。受験を見据えて、今からできることを一歩ずつ始めていきましょう!
四則演算をマスターする
中学受験の算数において、まず最初に身につけるべき力は「四則演算(+−×÷)」です。小数や分数を含む計算もスラスラできることが求められます。なぜなら、計算力がないと、勉強の効率が大きく下がってしまうからです。
たとえば、同じ60分の学習時間でも、計算に時間がかかる子は10問しか解けないのに対し、スラスラ解ける子は20問以上解けることがあります。この「差」がそのまま解法パターンに触れる量の差になり、結果として得点力の差につながってしまうのです。
中学受験の算数では、文章題や図形問題などさまざまなタイプの問題に触れる必要があります。しかし、いくら考える力があっても、計算に時間がかかると問題を解き切ることができません。「計算はできて当たり前」というレベルにまで引き上げることが、4年生の大切な目標です。
特別なことをやる必要はありません。まずは毎日少しずつ計算練習を続けること。これだけで確実に力はついてきます。地味な練習に思えるかもしれませんが、ここをおろそかにすると、どんなに考える力があっても受験算数の土俵にすら立てなくなってしまいます。というか、そもそも計算力がないのだから「考える力」もないと思います。
まずは、四則演算を「無意識でも正確に速くできる」レベルまで繰り返しましょう。それが中学受験算数への第一歩です。
逆算をマスターする
受験算数における「逆算」とは、等式の中に□(しかく)や文字が入った計算問題のことです。
たとえば、□+27=63 のような式を見たことがあるでしょう。これは、はっきり言えば方程式の考え方そのものです。
「中学受験で方程式を使ってもいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。たしかに、ラ・サールのような有名校を目指す場合、方程式に頼りすぎるのは良くないとされています。なぜなら、図や関係の整理で解ける問題を、わざわざ方程式に置き換えると、かえって時間がかかってしまうことがあるからです。
しかし、それでも逆算や消去算のような問題では、最低限の方程式の知識が必要になります。特に、算数に苦手意識がある子にとっては、逆算を「式」として処理することが大きな助けになることもあります。
大切なのは、「方程式を使うな」ではなく、「使いすぎない」ことです。考える道具のひとつとして、逆算を素早く解ける力を身につけておくことは、今後の学習の大きな土台になります。
まずは、□や文字を使った式に慣れ、落ち着いて解けるように練習を重ねていきましょう。それが、より難しい文章題や応用問題を解く力へとつながっていきます。
線分図は思考を可視化する武器になる
中学受験の文章題に取り組む上で、もっとも効果的な道具のひとつが「線分図」です。
文章をただ読むだけでは、数字の関係性や数量の増減を正確にイメージすることは難しいものです。そこで活躍するのが線分図。情報を図で“見える化”することで、頭の中を整理し、正しい方向で思考を進めることができるのです。
受験算数には、線分図のほかに「面積図」や「てんびん図」といった図の使い方もありますが、まずは線分図から始めるのがおすすめです。なぜなら、線分図は使いどころが多く、特に割合や差集め算、分配算など多くの文章題に対応できるからです。図が描けるようになると、式を立てるまでの時間が大幅に短縮され、正答率も上がります。
ただし、最初から上手に描ける子は多くありません。文章のどの部分をどう図に表すのか、最初は戸惑うこともあるでしょう。しかし、ここで大事なのは「正確さ」よりも「描いてみること」です。たとえ不完全でも、図を描こうとする習慣が身につけば、自然と図の精度も上がっていきます。
線分図は、まさに思考を可視化するための武器です。文章題でつまずく子の多くは、頭の中だけで考えようとしてしまい、情報を整理できていないケースが多いのです。図を使うことで、そうした混乱を防ぎ、問題を解く手がかりをしっかりとつかめるようになります。
まずは、毎日の学習の中で「とにかく線分図を描いてみる」ことを意識してみましょう。習慣化することで、算数の見え方がガラッと変わってくるはずです。
紙に書き出す習慣が思考力を育てる
中学受験の算数を学ぶうえで、意外と軽視されがちなのが「紙に書き出す習慣」です。
頭の中で何となく考えて、「うーん…」と悩んで止まってしまう――そんな時間を過ごしてしまう子も多いですが、これは非常にもったいないことです。
思考は、紙に書き出してはじめて“形”になります。
式、図、筆算、メモ――どんな形でもかまいません。まずは、目に見える形で考えを出すことが大切です。書き出してみると、今自分が何を理解していて、何がわからないのかが自然と見えてきます。
逆に、「書き出せない」というのは、「実は頭の中に考えがない」という状態です。
そのまま悩み続けても、前には進めません。だからこそ、まずは手を動かすこと、書きながら考えることがとても大事なのです。
書く習慣がある子は、問題の本質に早くたどり着けるし、ミスにも気づきやすい。思考のスピードも精度もどんどん上がっていきます。
これは、まるで筋トレやジョギングのようなものです。毎日少しずつでも取り組むことで、「考える体力」がついてきます。逆に、書かずに頭の中だけで考えていては、まるで「空想で筋トレやジギングをしている」ようなもので、成長は見込めません。
算数を得意にしたいなら、まずは「とにかく書く!」という習慣を、今日から始めてみましょう。地道な積み重ねが、やがて大きな力となって返ってきます。
【まとめ】4年生の今こそ、算数の土台をしっかり固めよう
中学受験において、算数は最も差がつきやすい科目です。だからこそ、4年生のうちに「計算力」「逆算の基礎」「図を使って考える力」、そして「紙に書き出す習慣」といった土台づくりをしっかり行うことが大切です。
今すぐ目に見える成果が出なくても、日々の練習の積み重ねが、5年生・6年生になったときの伸びにつながります。逆に、計算を疎かにしたまま5年生になると巻き返す可能性はかなり低いです。
5年生の内容から、本格的な中学受験の内容に入っていきます。それに比べると4年生の内容は肩慣らしみたいなものです。ここで勉強の習慣を身に付けられなかった人が5年生でついていけるとは思えません。
算数は特別な才能や難しいテクニックよりも、毎日の習慣と基本の反復が最大の武器になります。焦らず、慌てず、一歩ずつ。「できることを丁寧に」積み重ねていく姿勢が、最終的には志望校合格への最短ルートになります。
【保護者の方へ】家庭でできる小さなサポートが、大きな力になります
4年生のお子さまにとって、算数の勉強はときに苦しく、忍耐が必要な作業かもしれません。そんなときに、保護者の方ができることは「結果よりも過程をほめること」です。たとえ間違っていても、図を描いてみたこと、手を動かして考えたことに注目して声をかけてあげてください。
また、「紙に書き出すことが大事なんだよ」「線分図ってすごいね」などと共感の言葉をかけるだけでも、お子さまの学習意欲は大きく変わります。
中学受験は、親子二人三脚の長い道のり。ご家庭での小さな応援が、子どもたちの大きな自信と力につながっていきます。