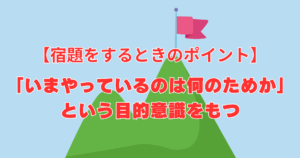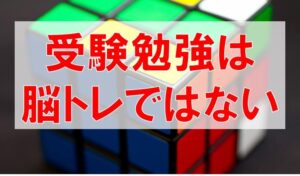頑張ってるのに伸びない理由|中学生の数学勉強の落とし穴
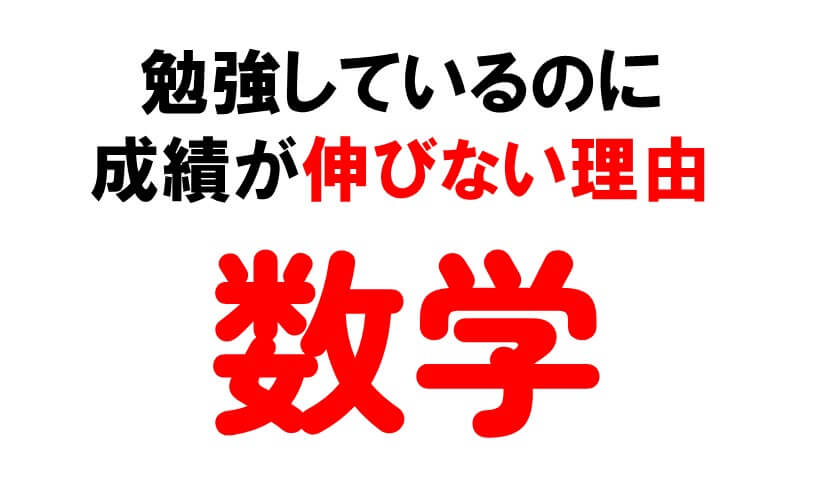
せっかくの自習が「時間のムダ」になる瞬間
中学生が真面目に机に向かい、数学の問題集に取り組んでいる――その姿だけを見れば、非常に「がんばっている」ように見えるでしょう。
しかし、その実態を観察していると、「この自習、時間の使い方としては非常にもったいない」と感じることが多々あります。努力が結果につながらない最大の原因は、「やり方」にあるのです。
1問に15分以上かけてしまう問題点
数学の問題を解くことは大切ですが、1問に15分以上もかけているとしたら、それは勉強として非効率です。特に、まったく歯が立たない問題に対して何も書かずにじっと悩み続けるのは、時間の浪費にしかなりません。
もちろん、ある程度難易度の高い問題で、途中の過程を自力で書き進めているなら、15分かける価値はあります。しかし、何も書けない、もしくは“とりあえず何か書いてみた”というレベルでただ時間を使い、進展がないなら、その15分は意味がありません。
数学は、漫然と時間をかければできるようになる科目ではありません。「考える」ことと「足を止める」ことは似て非なるものです。
手が動かないまま時間だけが過ぎていく
問題集を開いているものの、ノートがまっさらなまま時間が経過している――このような自習をしている生徒は少なくありません。手が止まっているということは、思考も止まっている状態であることがほとんどです。
このようなときは、すぐに解答を見て、「こう考えるのか」「この公式を使うのか」と確認すべきです。初見の問題で詰まったまま動かないのは、時間の無駄です。
自習時間は「わからないことを悩み続ける時間」ではなく、「知っていることを確認し、知らないことを取り入れる時間」にしなければ、学力は伸びません。
問題集レベルなら1時間で3ページ進めるべき理由
中学校で配布される一般的な問題集の難易度であれば、1時間で最低3ページは進めたいところです。これは、1ページあたり20分程度という計算です。
もちろん、応用問題であればペースは落ちても構いませんが、基本問題でこのペースすら守れないのであれば、学習のやり方に問題があります。
スピードを重視することで、「どこで詰まったのか」「どこで時間がかかるのか」がはっきり見えるようになります。そして、効率よく復習することができるのです。
「時間をかける=努力している」ではありません。正しい方向に時間を使わなければ、どれだけがんばっても成果は出ないのです。
考える前に、まず「知る」ことが先
「とにかく自力で考え抜け」「答えをすぐ見るな」と言われることがあります。たしかに、考える力を育てることは大切です。しかし、土台となる知識がまったくない状態で問題に挑んでも、時間だけが過ぎていくばかり。勉強は「知らないことを知ること」から始まるのです。
基礎がないうちは解答を見て覚えるべき
たとえば、中学生が因数分解の問題をはじめて見たとき、自力で解ける可能性はほとんどありません。公式もパターンも知らなければ、解き方の糸口すらつかめないのは当然です。
このとき必要なのは、「がんばって自力で解くこと」ではなく、「答えを見て解法の流れを理解すること」です。最初は、遠慮なく解答を見てください。そして、なぜそうなるのか、どういう順番で考えていくのかを、自分のノートに丁寧にまとめていくべきです。
これは「ズル」ではなく、正しい学習法です。
「考える力がつかない」という誤解
「解答を見たら、考える力がつかないんじゃないか」と不安に思う人もいるでしょう。けれど、それは大きな誤解です。そもそも“考える力”は、ゼロから生まれるものではありません。
料理に例えれば、包丁の使い方や食材の切り方、調味料の分量といった“知識”がなければ、どんな料理も作れません。カレーの作り方を何も知らずに「考えろ」と言われても無理があるのと同じです。
「考える」とは、「知っていることを組み合わせて、使いこなすこと」。何も知らないままでは、考える材料がないのです。
覚えた知識が、考える力の土台になる
数学の問題の多くは、「パターン」を知っているかどうかで決まります。たとえば、方程式の文章題であれば、「○○をxとおいて式を立てる」などの定型的な手順が存在します。これは“考えなくても手が動く”レベルで身につけるべき知識です。
こうしたパターンを十分にインプットしておくことで、応用問題に出会ったときに初めて「考える力」が発揮できます。逆に言えば、パターンを知らない状態で問題に取り組むのは、材料も道具もない状態で何かを作ろうとするようなものです。
まずはしっかり覚える。そして、覚えたことを使ってみる。その順序が、最も効率よく「考える力」を育てる道なのです。
復習」は、1回で終わらせない
「一度解けたから、もう大丈夫」――そう思って復習をしない生徒は多いですが、それでは知識は定着しません。むしろ、復習こそが学力を伸ばすカギです。特に数学のように積み重ねが重要な教科では、1回だけでは覚えられないことを前提に、何度も繰り返すことが必要です。
1回解いただけでは身につかない
人間の記憶は、時間が経てば忘れるようにできています。1回学んだだけの内容は、数日でほとんど忘れてしまうのです。
「前に解けたはずなのに、もう忘れてしまった」という経験は誰にでもあるはずです。それは、あなたの能力の問題ではなく、単に復習が足りていないだけ。つまり、何度も解き直すことで記憶は強化され、使える知識へと変わっていきます。
最低3回、難問は7回以上復習するつもりで
よく「復習は3回やればよい」と言われますが、これはあくまで基礎的な問題の話です。難易度が高い問題や、複雑な考え方を含む問題であれば、5回、7回と復習するのが普通です。
何度も同じ問題に触れることで、考え方や解法の流れが「当たり前の感覚」になります。逆に、1度しか解いていない問題は、ほとんどの場合、定着していないと考えた方がよいでしょう。
同じ問題を「わかっているつもり」で放置すると、いざというときに思い出せずに失点する原因になります。
自作の「解答ノート」を作るべき理由
復習の効率を上げるうえでおすすめなのが、「解答ノート」の作成です。これは、問題集の解答をそのまま写すだけではなく、自分の言葉でポイントや考え方を整理してまとめるノートです。
「解答があるのだから、見ればいい」と思うかもしれません。しかし、市販の解答は行間が省略されていたり、書き方が自分にとってわかりにくいこともあります。
そこで、自分で書き写すことで、以下のようなメリットが得られます。
- 解答の流れを自然と理解できる
- 自分の理解不足の箇所に気づける
- 後から見返したときに記憶がよみがえりやすい
また、解答を写す作業そのものが、「読む」よりもずっと記憶に残りやすいのです。
「めんどくさい」と思うかもしれませんが、このひと手間が大きな差を生みます。「ただ解く」ではなく「整理して残す」ことで、復習が意味のあるものになります。
解答ノートの作り方と活用法
「解答ノート」は、ただ問題の答えを写すだけのノートではありません。解き方の流れ・ポイント・注意点などを自分なりに整理してまとめる学習ツールです。丁寧に作ることで、復習効率が劇的に高まり、記憶の定着にもつながります。
行間を埋め、自分の言葉でまとめる
市販の解答や学校の配布プリントは、計算式や考え方の「途中」が省略されていることがよくあります。たとえば、計算の一部が一気に飛ばされていたり、「ここでなぜその式になるのか」が書かれていない場合も多いでしょう。
そのまま写すだけでは、自分がつまずいた原因を解決できません。
だからこそ、「なぜそうなるのか?」という行間を、自分の言葉で補って書くことが重要です。
たとえば──
- なぜこの式を立てるのか?
- このミスはどこで起こったのか?
といったことをメモや吹き出しで書き加えていくことで、自分だけの理解ノートが完成します。
読み返しやすく、復習効率が上がる
一度作った解答ノートは、後日復習するときの強力な味方になります。
問題集の解答よりも、自分のノートの方が「自分がどこでつまずいたか」「どう考えたか」がわかるため、記憶がよみがえりやすく、理解が深まりやすいのです。
また、自分の字・自分の表現・自分の言葉でまとめられたノートは、感覚的に頭に残りやすく、効率よく復習→定着というサイクルを回すことができます。
復習時に「また詰まる」という無駄をなくすためにも、見返しやすいノート作りはとても有効です。
1問5~20分かけて丁寧に作る意味
「1問にそんなに時間をかけるなんて、非効率では?」と思うかもしれませんが、“解答ノートを作る”という行為は、ただの復習ではなく「頭の中を整理する作業」でもあるのです。
- 手を動かして書く
- 「わかるつもり」の曖昧さを自覚する
この一連の流れを通じて、問題に対する理解が深まり、定着率が格段に上がります。
とくに重要な問題や、何度も間違える問題は、5〜20分かけてでも丁寧にノートを作る価値があります。短時間で「またわからない」を繰り返すよりも、1回しっかり取り組む方が、結果的に時間の節約になります。
まとめ|努力を結果につなげる正しい勉強法を
「ちゃんと机に向かっているのに、なぜか成績が上がらない」
「がんばっているつもりなのに、テストでは点が取れない」
そう感じている中学生は少なくありません。しかし、それはあなたに「やる気」が足りないからではなく、やり方が間違っているからかもしれません。
「がんばってるのに成果が出ない」は勉強法の問題
「一問に長時間悩む」「一度解いて満足する」「解答を見ずに自力でやろうとする」――
このような自己流の学習では、時間だけが過ぎ、知識も身につかず、結果にもつながりません。
努力しているのに伸びないのは、「がんばっていないから」ではなく、「がんばり方」が間違っているからです。正しい手順で、正しい勉強を積み重ねれば、誰でも少しずつ結果を出せるようになります。
自己流より、正しい方法で積み上げよう
勉強において大切なのは、「がんばること」よりも「どうがんばるか」です。
- 自力で解けなくて当然の問題は、まず解答を見て理解する
- 解けた問題も、最低3回以上は復習する
- 自分だけの「解答ノート」を作って、復習しやすくする
こうした工夫を取り入れるだけで、同じ1時間の勉強でも得られる成果が大きく変わります。
勉強に近道はありませんが、無駄な遠回りは避けられます。
正しい方法を知って、確実に積み上げていくことで、「勉強ができる自分」に変わっていけるのです。